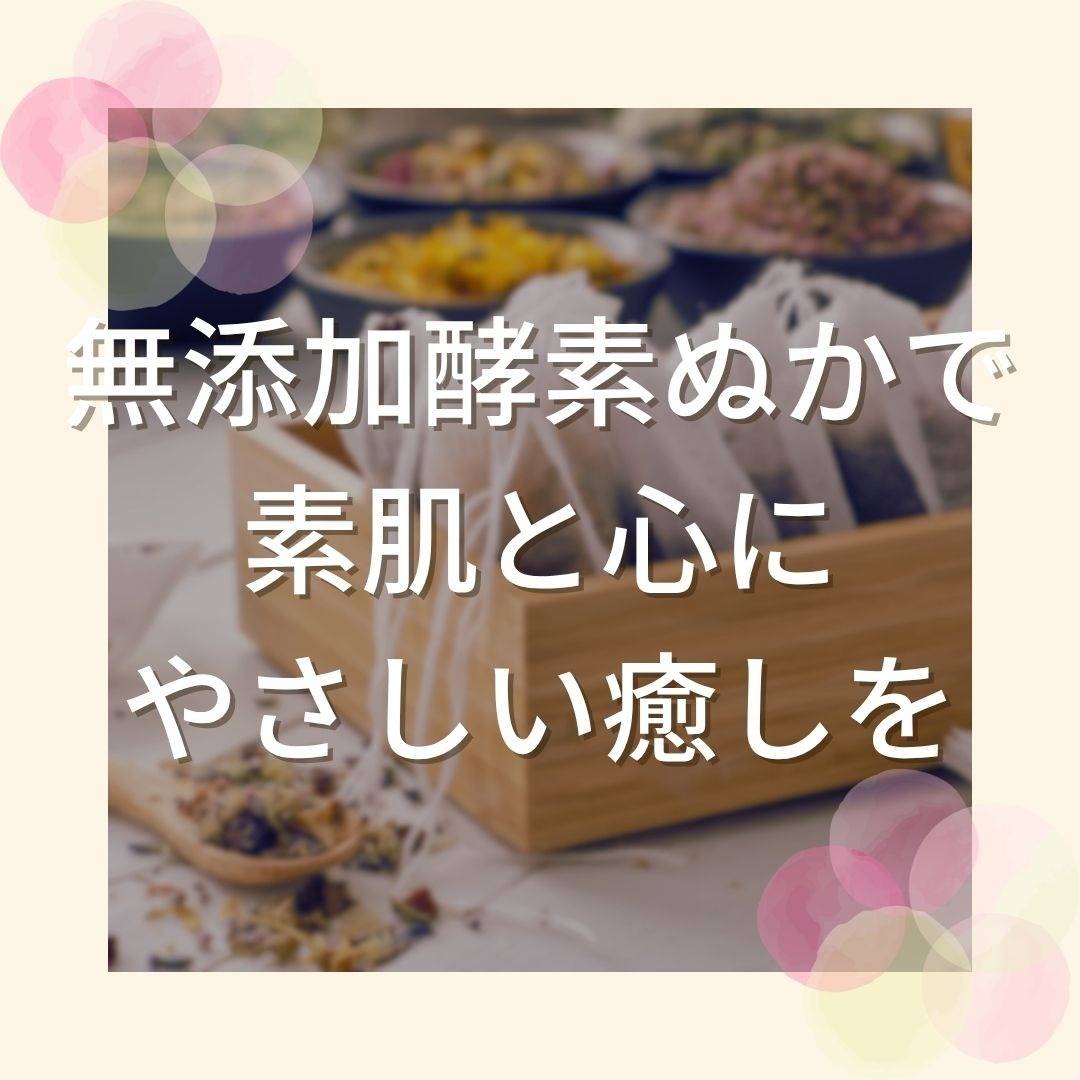米作りの現場から〜猛暑での最後の水管理
2025/09/02
今年の稲と水管理レポート:猛暑年ならではの“見極め”
今年の田んぼは、いつもの「水を切る時期」とはまるで違う表情です。例年なら、米の身(登熟)が進んで黄色みが増す頃には水を抜き、自然乾燥で仕上げに入ります。しかし、今年は40℃に迫る(あるいは超える)猛暑日が続き、同じ圃場の中でも黄色く進んだ株と、まだ青い稲穂が混在。その見極めと水管理が品質を左右しています。
黄色い穂と青い穂、どう見分けてどう潅水するか
• 黄色く色づいた穂:基本はもう水を必要としません。水を切って根を休ませ、倒伏や過剰な軟化を防ぎます。
• まだ青い穂:登熟の真っ最中で、**水が不足すると「しなび」「乾燥」「焼け」**が起きやすい。粒張りを守るために、土面が熱を持つ時間帯を避け、**浅水で“涼を取らせる”**意識で潅水します。
40℃級の年に起きること
通常なら今の時期(本来は日中30℃以下が理想)に水を切っても問題ありませんが、今年のような極端な高温では、土壌面が灼けて稲体がダメージを受けます。殻が焦げたように籾殻が暗く焼けるのが高温障害のサイン。とはいえ今年は不思議と、「暑いのにまだ焼けていない」圃場があるのも事実。
これは、こまめな浅水管理と夜間のクールダウン潅水が効いている可能性があります。日中は水温が上がりすぎるので、水を張るなら夕方〜夜明け前を基本に。昼は水を深くし過ぎないことがポイントです。
台風前後の水の入れ方
台風接近時は、**「暴れないように、あえて水をいっぱい張る」**のが鉄則。水の重みで茎葉が風にあおられにくくなり、根の露出や泥はねによる病害誘発を抑えられます。
• 前日:用水を確保し、やや深水に。排水路の詰まりを事前に点検。
• 通過後:倒伏と冠水の有無を確認。濁水は早めに入れ替え、浅水→間断潅水で再スタート。高温が戻る見込みなら、夜間潅水の体制を継続。
今年の“仕上げ”の考え方
• 部分最適でOK:同じ田でも成熟度がばらつく年。区画ごとに水管理を変える勇気を。
• 「焼け」予防を優先:見た目が黄化しても、日中の地温が高い日は急な水切りを避ける。
• 夜に稲を休ませる:夜間の浅水で稲体温を落とし、登熟を守る。昼は風通しを確保。
観察メモ(現場の実感)
• 黄色化した株は落ち着いている。
• 青い稲穂は水が切れるとすぐにしなび、葉先が乾いて「焼け」へ。
• 今年は猛暑にもかかわらず、籾殻の焦げ(暗化)が少ない圃場も。的確な潅水タイミングが奏功している可能性。
• 例年なら水を切る時期でも、今年は“涼水管理”を続ける価値あり。
まとめ
今年は「カレンダーどおり」に仕上げない年。稲の色・葉先の張り・籾の状態を見て、夜浅水・昼控えめ・台風前は深水を基本に、局所対応で品質を守る。
高温年の米作りは、最後の一手が勝負。**“水は栄養”ではなく“温度調整”**と捉え、稲を焼かせず、粒張りを守る水管理で収穫へ繋ぎます。